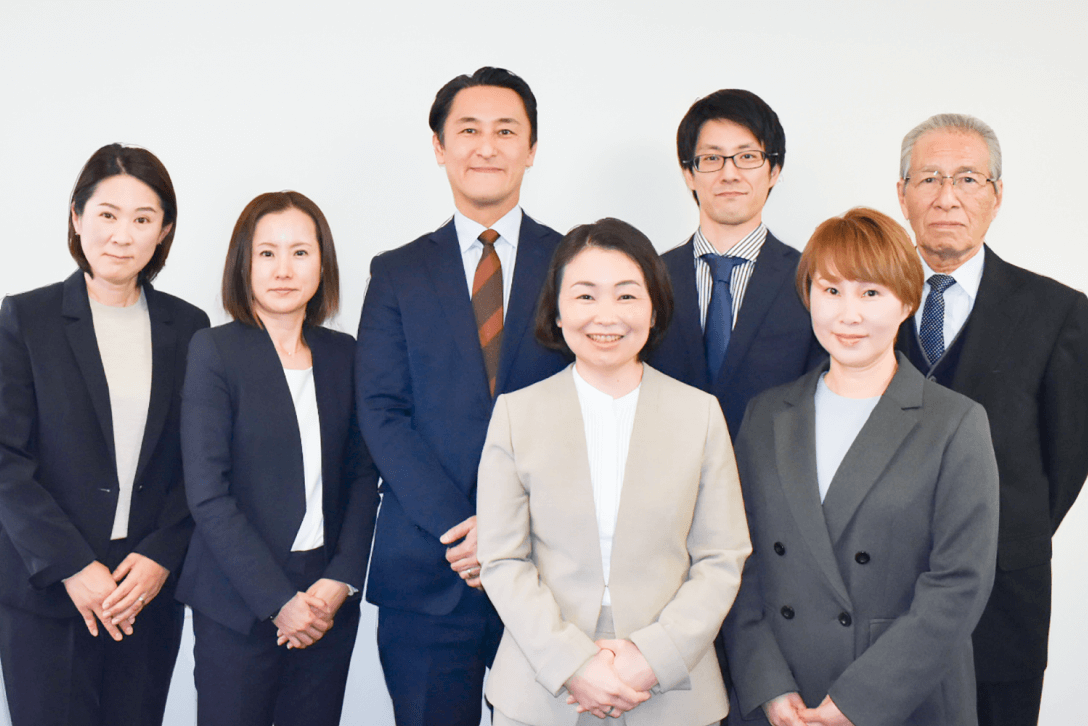
シーガル法務事務所について
「初めてのことで不安を感じている」「慣れないことで戸惑っている」「日々のことで忙しく時間が取れない」もしそのようにお悩みでしたら、是非当事務所にご相談ください。当事務所では、お客様の負担を最小限にすることを最優先に考え、スタッフ全員が明確かつ分かりやすい説明とスムーズな対応を心がけております。また豊富な知識と経験で、お客様に最適なリーガルサービスの提供をいたします。
サービス
相続手続き丸ごと
サポート
165,000円~
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)とは、全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
【このような方が対象】
- 仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない
- 相続人が多くて遺産分割や書類のやり取りが大変
- 財産の種類が多岐にわたっている
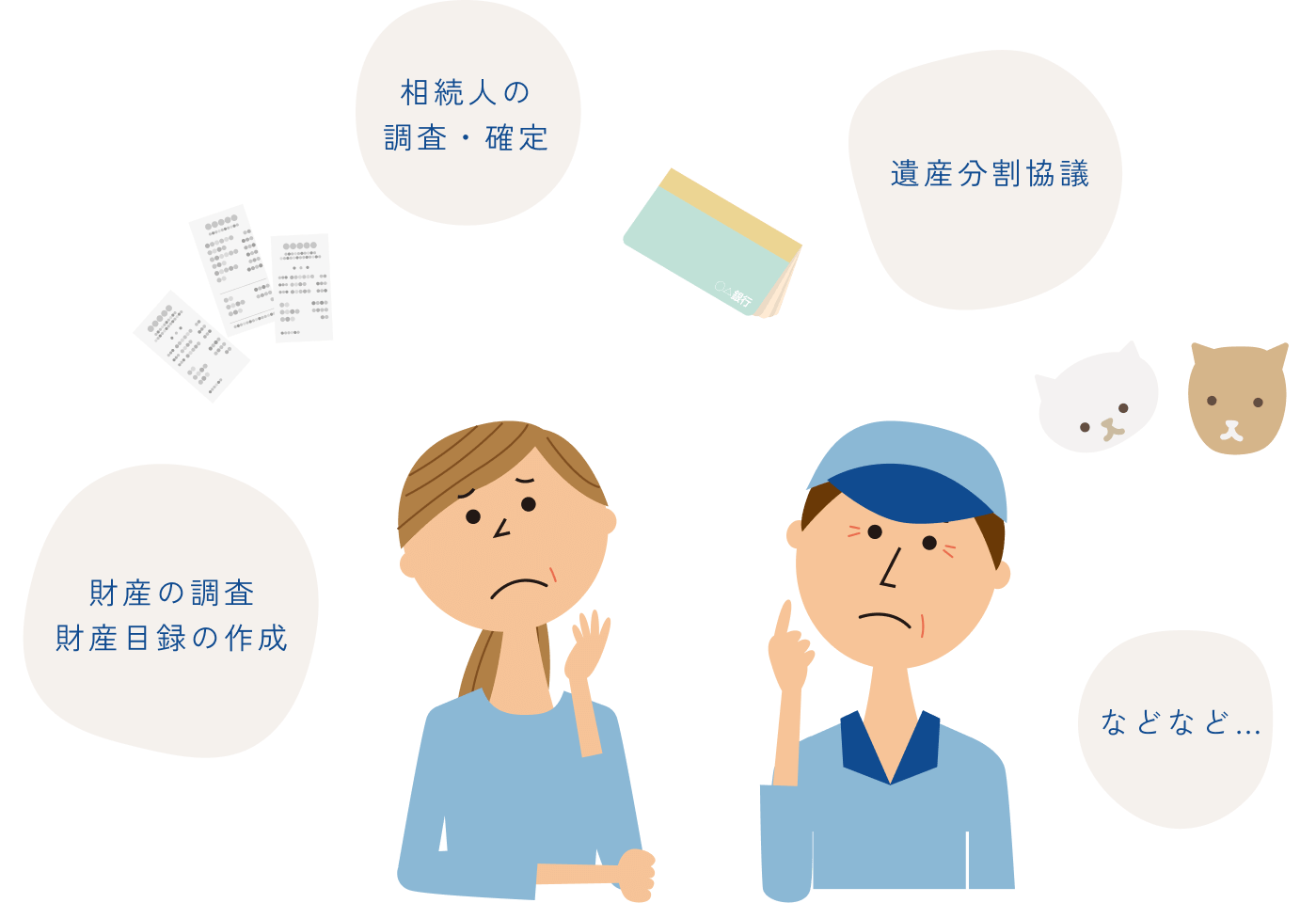
その他のサービス
-

相続登記
55,000円~
【このような方が対象】
- 不動産の相続登記をしたいが、何から手を付ければいいかわからない
- 相続手続きのうち、不動産の手続きだけ頼みたい
-
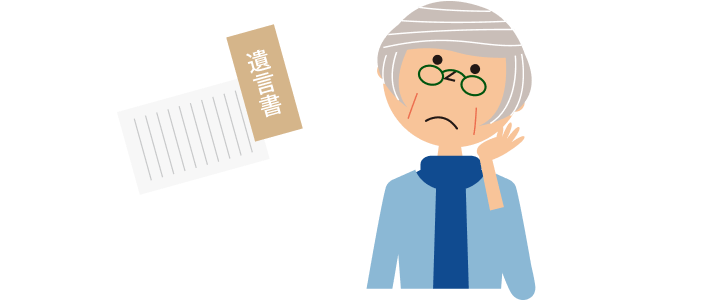
遺言書作成
33,000円~
【このような方が対象】
- 遺言書の内容はある程度決めているが書き方がわからない
- 公正証書遺言を作成したい
-
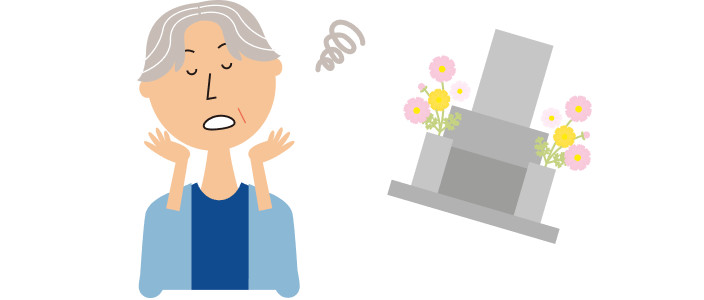
生前対策
330,000円~
【このような方が対象】
- 自分にとって最適な生前対策を考案してほしい
- 将来家族が認知症になるかもしれなくて心配
- 相続税が発生しそうなので、事前対策が必要
-
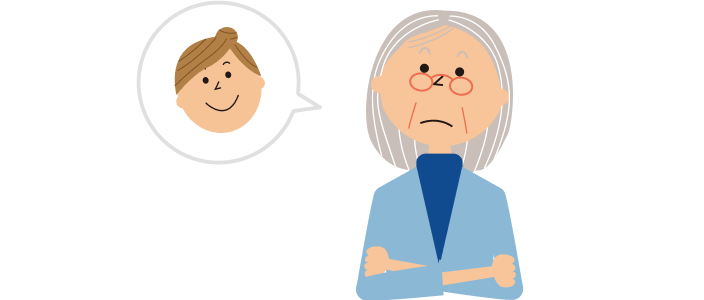
家族信託サポート
330,000円~
【このような方が対象】
- 認知症の対策をしたい
- 相続、生前対策をしたい
- 空き家の対策がしたい
-
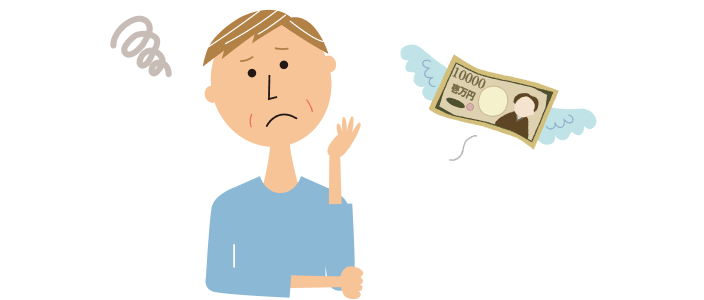
相続放棄
11,000円~
【このような方が対象】
- 親の借金を相続したくない
- 親族間の相続の争いに巻き込まれたくない
-
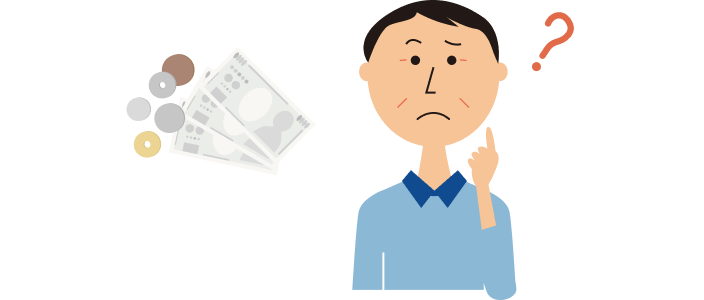
相続税申告サポート
お見積もり
【このような方が対象】
- 相続税申告について税理士に相談したいが自分で探すのが不安
お客様に選ばれる
5つの理由
-
相続に強みを持つ事務所
3000件以上のご相談実績を持つ
司法書士が対応 -
ワンストップ対応
弁護士をはじめとする
様々な専門家と連携 -
抜群の機動力
若さを武器に
時間、場所、移動に柔軟な対応 -
地域密着
地域社会に奉仕し、
世代を超えたお付き合い -
アクセス良好
東海道線辻堂駅から徒歩1分
駅周辺の駐車場も多数
まずは
無料ご相談で
相続のお悩みを
お伺いします!
初回の相談は無料です。
ご相談はご来所、Zoomなどのオンラインも可能です。お気軽にお問い合わせください。
投稿はまだありません。
投稿はまだありません。
投稿はまだありません。



